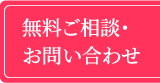左足の痺れの症例
こんにちは^_^新ノ口駅から徒歩5分で鍼灸接骨院と漢方薬店を営んでいる、ぐっさんです。
今日は左下腿部の痺れの症例を書きたいと思います。
患者の年齢は30代男性で、普段は疲労をとる漢方を飲んでいると体調が良い方です。
最近気温が低くなってからだんだんと左下腿部の痺れがきつくなってきたと何とかならないかと相談を受けました。
痺れが特に強く感じるのが特に朝起きがけだということと、小便の量が寒くなってから少なくなっている事から金匱要略の痓濕暍病の湿病ではないかと考えました。
朝が特に症状がきつい事から、曰晡所劇(一般的に午後3時〜午後5時ぐらいの陰気と陽気が入れ変わる時間帯の事をいいますが湿の症状と半表半裏の症状は非常によく似ています。ただ、曰晡の解釈をもう少し拡大解釈をすると、夕方にあるなら、朝方にでも同様に起こりえると考えてあげると非常に捉えやすくなると思います。)ととらえて湿ではないかと考えました。
今回は、下腿部の痺れる症状が古典の条文そのままだったので、を使用する事にしました。
いつも2週間に一度来院される患者さんなので、2週間分の湿気をとるものをお渡ししたところ、1週間ほどで、痺れの症状がなくなったそうです。
古方の考え方の参考になったら幸いです。